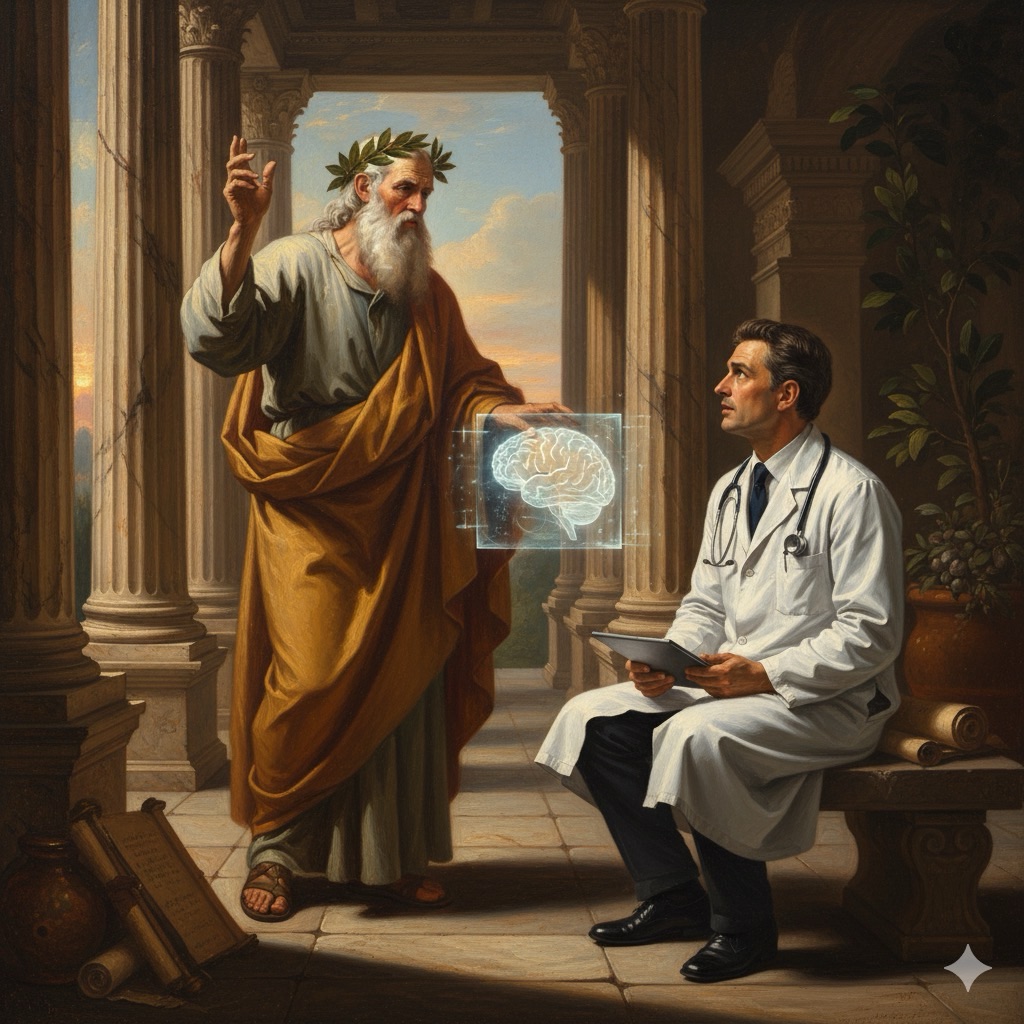あなたは「勝てないゲーム」をプレイし続けていないか?
職場の人間関係、パートナーとのすれ違い、親子間の確執──。我々の人生は、無数の「対人関係ゲーム」で構成されている。そして多くのプレイヤーは、どうすれば勝てるのか、そもそもこのゲームに勝ち筋はあるのかさえ分からぬまま、同じような失敗を繰り返しながら疲弊していく。
かつての私も、そんな出口のないゲームのプレイヤーの一人だった。
例えば、指導医として後輩の指導にあたっていたときのことだ。なかなか成長しない部下に対し、私は善意の仮面を被り、マイクロマネジメントという名の監視を続けた。結果、彼は主体性を失って萎縮し、私は「慕われる先輩」どころか「最も煙たい存在」になった。チームの生産性は地に落ち、残ったのは徒労感だけだ。
恋愛というゲームでは、さらに悲惨な戦略をとった。パートナーに嫌われまいと、過剰なまでに尽くし、相手の要求をすべて受け入れた。自分の時間をすべて捧げ、高価なプレゼントを贈り続けた。この戦略の結末は、言うまでもない。彼女は私の献身を当然の権利とみなし、最終的には別の相手のもとへ去っていった。
なぜ、こんなことが起きるのか?なぜ、良かれと思って選択した戦略が、ことごとく裏目に出るのか?それは、我々がインストールしている人生のOS(オペレーティング・システム)そのものに、深刻なバグが潜んでいるからに他ならない。
我々を縛る「原因論」という名のバグ
我々のデフォルトOSは、フロイト的な「原因論」でプログラムされている。
「過去の出来事(原因)が、現在の自分(結果)を決定づける」という、一見すると揺るぎないロジックだ。
私自身、このバグに深く侵されていた。私には、非常に厳格な父親がいた。常に完璧を求められ、できていない部分だけを虫眼鏡で拡大するように指摘される。そんな環境で育った(原因)せいで、自分は他人の顔色ばかりうかがい、自分の意見を主張できない、どこか捻じ曲がった性格になってしまった(結果)のだと、半ば諦めと共に規定していた。
この「原因論」は、一種の麻薬だ。過去のせい、環境のせい、他人のせいにしている限り、自分は「被害者」でいられる。変われない自分を正当化し、行動しないことへの完璧な言い訳を与えてくれるからだ。
だが、その代償はあまりに大きい。我々は過去の奴隷となり、人生の操縦桿を自ら手放すことになる。この深刻なバグに気づき、OSを書き換えるためのパッチ(修正プログラム)を提示したのが、アルフレッド・アドラーの心理学だ。そして、その衝撃的な思想を現代に蘇らせたのが、ベストセラー『嫌われる勇気』である。

OSを書き換える劇薬「目的論」
アドラーは、原因論という常識を根底から覆す。彼は「トラウマなど存在しない」と断言し、代わりに「目的論」という新たなOSを提示する。これは、「人間の行動は、過去の原因ではなく、未来の“目的”によって決定される」という、にわかには信じがたい思考実験だ。
この新しいOSで、先ほどの私の失敗を再インストールしてみよう。
部下へのマイクロマネジメント。私の表向きの目的は「彼を育てる」ことだった。だが、目的論の視点に立てば、本当の目的は全く別のところにあると気づかされる。それは「部下が失敗することで、指導者である自分の評価が傷つくのを避ける」「すべてを自分の管理下に置き、不確実性というストレスから解放されたい」という、自己中心的な目的だ。その身勝手な目的を正当化するために、「教育」という大義名分を創り出していたに過ぎない。
恋人への過剰な献身も同じ構造だ。表向きの目的は「相手への愛」だが、その裏に隠された本当の目的は「相手を自分に依存させ、コントロールすることで、見捨てられる不安を解消する」ことだったのかもしれない。私の戦略は、愛ではなく、支配だったのである。
そして、私を長年縛り付けてきた父親との関係。私は「父のせいだ」と嘆くことで、「対人関係のタスクから逃げ、傷つくリスクを回避する」という目的を達成していたのだ。捻じ曲がった性格は、父によって作られたのではなく、私が自らの目的のために「選択」したものだったのだ。
これは、残酷な真実だ。しかし同時に、希望でもある。我々の人生が、変えられない過去ではなく、「いま、ここ」で設定する目的によって動いているのなら、我々はいつでも人生を再起動できるからだ。
この思考のOS書き換えは、一度や二度読んだだけでは難しい。思考の癖を修正するには、反復練習が必要だ。多忙な現代人にとって、移動時間や家事をしながらでも、耳からこの新しいOSをインストールできるAudible(オーディブル)の聴く読書は、極めて合理的な投資となるだろう。最初の1冊は無料で体験できる。このチャンスを逃す手はない。
人生の主導権を取り戻すための第一歩
OSを書き換えると決意したとき、我々は人生の操縦桿を初めてその手に取り戻す。過去の奴隷であることをやめ、自らの人生の創造主となるのだ。
もちろん、言うは易く行うは難し。アドラーが提唱する最終目標である「共同体感覚(他者を仲間とみなし、そこに貢献していくこと)」などは、私自身、まだ実践できているとは到底言えない。
だが、絶望する必要はない。重要なのは、いきなり完璧を目指すことではない。アドラーの思想は、小さな第一歩から始めることを許容する。それは、「他者との比較をやめる」ということだ。
我々は常に、SNSの中にいるキラキラした同僚や、先を行くライバルと自分を比較し、劣等感に苛まれる。しかし、その土俵に上がる必要はない。比べるべき相手は、ただ一人。「昨日の自分」だ。昨日より一行でも多く本を読めたか。昨日より一つでも多く、新しい知識を得られたか。その小さな進歩に価値を見出すこと。それこそが、健全な劣等感の第一歩となる。
そして、この「対人関係ゲーム」のバグを修正するための、最も強力で、最も実践的なプログラムこそが、「課題の分離」という概念だ。部下を管理しようとして失敗したのも、恋人に尽くしすぎて自滅したのも、すべてはこの「課題の分離」ができていなかったことに起因する。
この考え方を知ったとき、私は文字通り目の前の霧が晴れるような感覚を覚えた。それは、他人に振り回される人生に終止符を打ち、自分という名の航路を切り拓くための、羅針盤だった。
次回は、この「課題の分離」という最強のツールについて、さらに深く掘り下げていく。