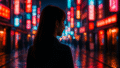医師のためのマイクロ法人活用術:節税と社会保険の最適化を実現する方法
はじめに:あなたの手取りは、思っているより少ない
「医師=高所得者」と思われがちですが、実際に手元に残る金額は、税金と社会保険料でかなり削られています。
年収1,500万円の医師でも、住民税・所得税・健康保険・年金の支払いで、実質の手取りは50%未満というのが現実です。
この問題に対する“制度的な対抗策”として注目されているのが、マイクロ法人の活用です。
マイクロ法人とは?──個人所得と法人所得の分離戦略
「マイクロ法人」とは、1人または家族数名で運営する極小規模の法人(株式会社または合同会社)のこと。
医師がこの法人を設立し、個人と法人を税務上分離することで、所得税・社会保険料を最適化することができます。
基本構造:
- 代表者:本人(医師)
- 収入の一部を法人名義で受け取る
- 家族を役員として雇い、所得分散も可能
- 法人経費を活用し、課税対象を合法的に圧縮
どこで得をする?──税金と社保の「W最適化」
医師が法人を使うと、主に以下の2点で経済的メリットがあります:
1. 所得税の削減
個人の高額報酬(最大45%課税)を法人所得(15〜23%)に切り替えることで、実効税率が劇的に下がる。
2. 社会保険料の削減
役員報酬を月額5万円に設定すると、協会けんぽ加入でも年間保険料は20〜25万円程度に抑えられる。
ケーススタディ:年収1,500万円の医師
| 区分 | 勤務医 | マイクロ法人(報酬月5万円) |
|---|---|---|
| 所得税+住民税 | 約500万円 | 約250万円 |
| 社会保険料(本人+法人) | 約200万円 | 約25万円 |
| 手取り | 約800万円 | 約1,200万円(法人内部留保含む) |
このように、年間400万円近い差が生まれる可能性があります。
※このケーススタディでは、総年収1,500万円のうち「勤務医としての給与収入500万円」「法人契約による業務収入1,000万円」という前提で試算しています。法人側からの役員報酬は月額5万円(年間60万円)とし、残りは法人内に留保したケースです。
注意点:勤務医の報酬は法人で受け取れない
法人活用で最も多い誤解が「病院の給料も法人で受け取れるのでは?」というものです。
結論から言えば、病院との雇用契約による給与収入は法人では受け取れません。
ではどうするか?
副業として法人が請け負える仕事を確保する必要があります。
法人で受け取れる「副業」例(医療系でOK)
- 医療記事の執筆、監修
- 講演会・セミナー講師
- 学会運営協力
- 遠隔読影
- クリニック向けIT・経営コンサル
これらは医師免許を活かしつつ、業務委託契約で法人に収益を入れることが可能です。
法人設立のステップ
- 業務内容の確立(法人で何をするか明確に)
- 合同会社または株式会社を設立(6万円〜)
- 法人名義の契約書・口座を用意
- 税理士に相談し、報酬と経費のバランス設計
- 年次決算・帳簿作成をルーティン化
よくある質問と誤解
Q1. 医療法人とは何が違う?
→ 医療法人は診療所運営用。マイクロ法人はそれとは別で、自由度が高い。
Q2. 副業がないと意味がない?
→ その通り。法人で売上が立たないと節税メリットは生まれない。
Q3. 家族を役員にしても大丈夫?
→ 実際に業務をしていればOK。形式だけは税務署に否認されるリスクあり。
まとめ:医師の未来は“法人化”が握る
マイクロ法人は、医師という専門職の資産形成において極めて強力なツールです。
勤務医としての働き方とは切り分けて、副業を通じて法人収入を得る構造を作ることで、合法的な節税と社保負担軽減が可能になります。
“手取りを増やす”だけでなく、“自分の人生を守るもう一つの財布”として、今こそマイクロ法人という選択を。
筆者について
匿名のフリーランス医師。内科系サブスペ専門医。マイクロ法人を使った節税・資産形成を実践中。ブログ・Xにて情報発信中。→ フリーランス医タケル@FIRE