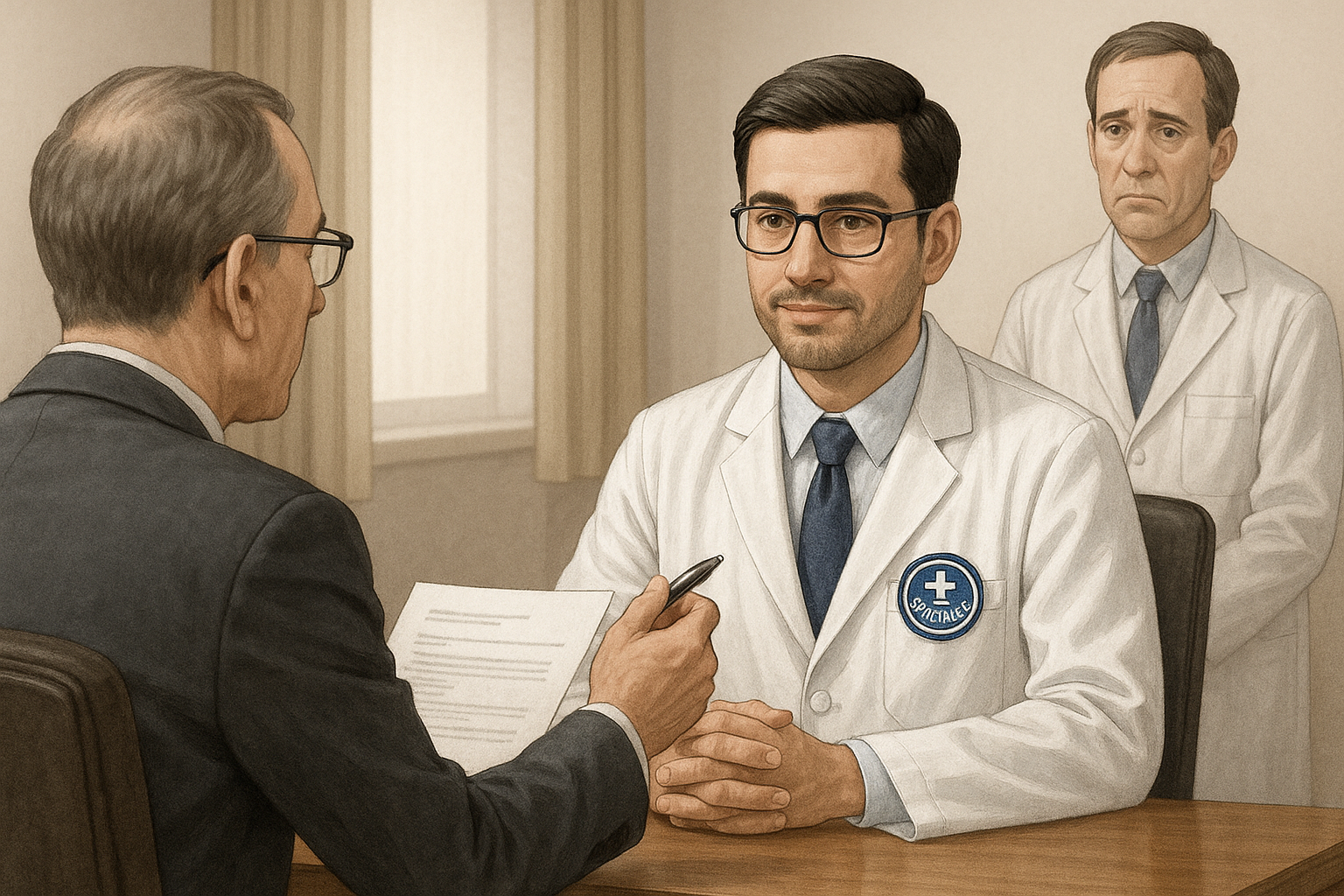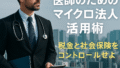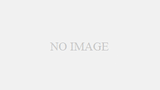「専門医なんて、コスパが悪すぎる」――。そう嘆く若手医師の声が聞こえてくる。彼らの主張は、驚くほど合理的だ。数年間にわたる大学病院での研修という名の奴隷労働。薄給で身を粉にし、膨大な症例報告と論文作成に追われる日々。その苦行の末に専門医資格を手にしても、国が定める診療報酬が上がるわけでもなければ、勤務先の給与が劇的に改善されるわけでもない。これは紛れもない事実だ。
閉鎖的なムラ社会(=医局)の中で、上の命令に従順に働き続ける限り、専門医資格は単なる「通過儀礼」に過ぎないのかもしれない。時間と労力を一方的に搾取されるだけの、きわめて「コスパの悪い自己投資」。若手がそう結論づけるのも無理はない。
だが、その常識は「医局」という名の保護ケージを一歩外に出た瞬間、木っ端微塵に砕け散る。自らの力で労働市場の荒波を泳ぎ始めるとき、あの「コスパの悪い」はずだった資格が、生命線ともいえる「品質保証マーク」として機能し始めるのだ。
目次
1. なぜ専門医資格は「JISマーク」なのか?
我々は、この国の労働市場で取引される「商品」であるという現実を直視しなければならない。そして、専門医資格とは、その商品に付与された「JISマーク(日本産業規格)」に他ならない。
想像してみてほしい。あなたが家電量販店でエアコンを買おうとしている。性能もデザインもほぼ同じ、価格も似たような2つの製品が並んでいる。片方には、品質を保証する「JISマーク」がついている。もう片方には、何もない。あなたはどちらを選ぶだろうか?答えは言うまでもない。よく分からないメーカーの、品質保証のない製品に手を出すリスクを、あなたは決して取らないはずだ。
専門医制度に様々な問題があることは事実だ。しかし、それでもなお、第三者機関が一定のトレーニングと知識、経験を客観的に評価し、保証する現行の仕組みは、この国における唯一無二の「品質保証システム」として機能している。これに代わる客観的な指標は、今のところ存在しない。
2. 採用担当者(特に非医師)の冷徹な視線
この「JISマーク」の価値が最も発揮されるのは、医師が新たな勤務先を探す「転職市場」である。特に、採用の最終決定権を握るのが院長ではなく、非医師である事務長や経営者である場合に、その威力は絶大となる。
彼らにとって、医師個人の技量や人柄など、完全にブラックボックスだ。学会でどんなに高名だろうが、どれほど神がかった手技を持っていようが、それを客観的に評価するモノサシを彼らは持たない。彼らが信頼できる唯一の情報、それは「履歴書に記載された客観的な事実」だけだ。
無数の応募書類が送られてくる中で、彼らが最初に行う作業は何か?「足切り」である。そして、その最も分かりやすく、かつ合理的なスクリーニングの基準が「専門医資格の有無」なのだ。「専門医」というJISマークがある医師だけを残し、それ以外は検討のテーブルにすら載せずにゴミ箱へ送る。これが、採用の現場で日々行われている冷徹な現実である。
3. JISマークのない家電は、そもそも土俵に上がれない
もちろん、JISマークさえあれば全てが安泰だという楽観論を語るつもりはない。JISマークは、あくまで「最低限の品質が保証されている」ことを示すに過ぎず、それが「超高性能である」ことの証明にはならない。市場で高く評価されるためには、JISマークを土台とした上で、コミュニケーション能力や経営的視点といった、さらなる「付加価値」を実装していく必要がある。
しかし、ここで絶対に誤解してはならないことがある。議論の順序が逆なのだ。我々が問うべきは「JISマークがあれば成功できるか?」ではない。「JISマークなしで、そもそも戦いの舞台に立てるのか?」である。
答えは残酷なまでに明確だ。ノーである。品質保証のない家電が比較検討の対象にすらならないように、専門医資格を持たない医師は、多くの採用市場において「存在しない者」として扱われる。あなたの持つ本当の価値をプレゼンテーションする機会すら、与えられないのだ。
結論:コスパを超えた「市場への入場券」
若手医師が感じる「専門医はコスパが悪い」という感覚は、医局という閉鎖された世界の中でのみ通用するローカルな真実だ。一度市場に出れば、その資格は「コスト」から「必須の資産」へとその価値を劇的に変える。
専門医資格の取得は、輝かしいゴールではない。それは、あなたがプロフェッショナルとして、この国の残酷な労働市場に参加するための「最低限の入場券」にすぎないのだ。その入場券を手に入れなければ、試合は始まらない。コスパを云々するのは、リングに上がってからの話である。