「自由」とは、選択肢を減らすことではない
最近、「専門医なんかいらない」という若手医師たちの声を見かける。彼らは「医局に縛られずに生きたい」「好きな場所で自由に働きたい」と語る。しかし、それは本当に“自由”なのだろうか?
専門医という資格は、必須ではないかもしれない。しかし、それを持たないことで将来の選択肢が減ってしまうことは意外と気づかれにくい。つまり、「資格を取らない自由」の代わりに、「選べない未来」という不自由がやってくるかもしれないのだ。
専門医とはJISマークのようなもの
専門医という資格は、医師の実力を完全に保証するものではない。だが、少なくとも「この人は一定の基準を満たしている」という“証明”にはなる。
これはまるで、家電製品のJISマークのようなものだ。たとえば、エアコンにJISマークがなかったら、あなたはその製品を安心して買うだろうか?買い手にとっては、性能そのものより「保証があること」が大きな安心材料になる。
医療の現場でも同じことが言える。病院や患者が、あなたの腕前を知る術は限られている。その中で「専門医あり」と書かれていれば、少なくとも“素性の知れた医者”として信頼のスタートラインに立てる。
専門医を持たないリスク
フリーランス医や地方医療など、専門医がなくても働ける場は確かにある。しかし、それはあくまで「現時点の状況」でしかない。
将来、何らかの事情で都市部に戻りたいとき。家族の都合で働き方を変えたいとき。医師としてのキャリアを広げたいとき。そうした場面で「専門医を持っていないこと」が思わぬ足かせになる。
資格は、選択肢を持ち続けるための“保険”のようなものだ。使わない自由もあるが、持っていないと選べない未来もある。
「専門医制度=搾取」という誤解
一部の若手医師の中には、「専門医制度は医局による搾取の道具だ」と考える人もいる。確かに、医局制度には時に旧態依然とした部分があり、若手を過酷に扱う現場も存在する。
しかし、だからといって「専門医なんか要らない」と切り捨ててしまうのは、本質を見誤っている。
問題なのは制度そのものではなく、それを運用する人間の側だ。制度をどう活かすか、あるいはどう距離を取るかは、自分次第で決められる。専門医制度を“搾取”と見るか“武器”と見るかで、その後のキャリアの自由度は大きく変わってくる。
結論:資格とは、使わないために持っておくもの
資格とは、「使うため」に取るものではなく、「使わなくても済むように」持っておくものだ。必要なときに備えて持っておく。これが、本当のリスク管理であり、真の意味での“自由”を確保する手段なのだ。
「専門医なんか要らん」と断言する前に、数年後の自分がどういう場所で、どういう働き方をしているか、その可能性を自ら狭めていないか、立ち止まって考えてみてほしい。
自由とは、自分で未来を選べる状態をいう。
そのために、専門医という“チケット”を捨ててしまうのは、あまりにももったいない。
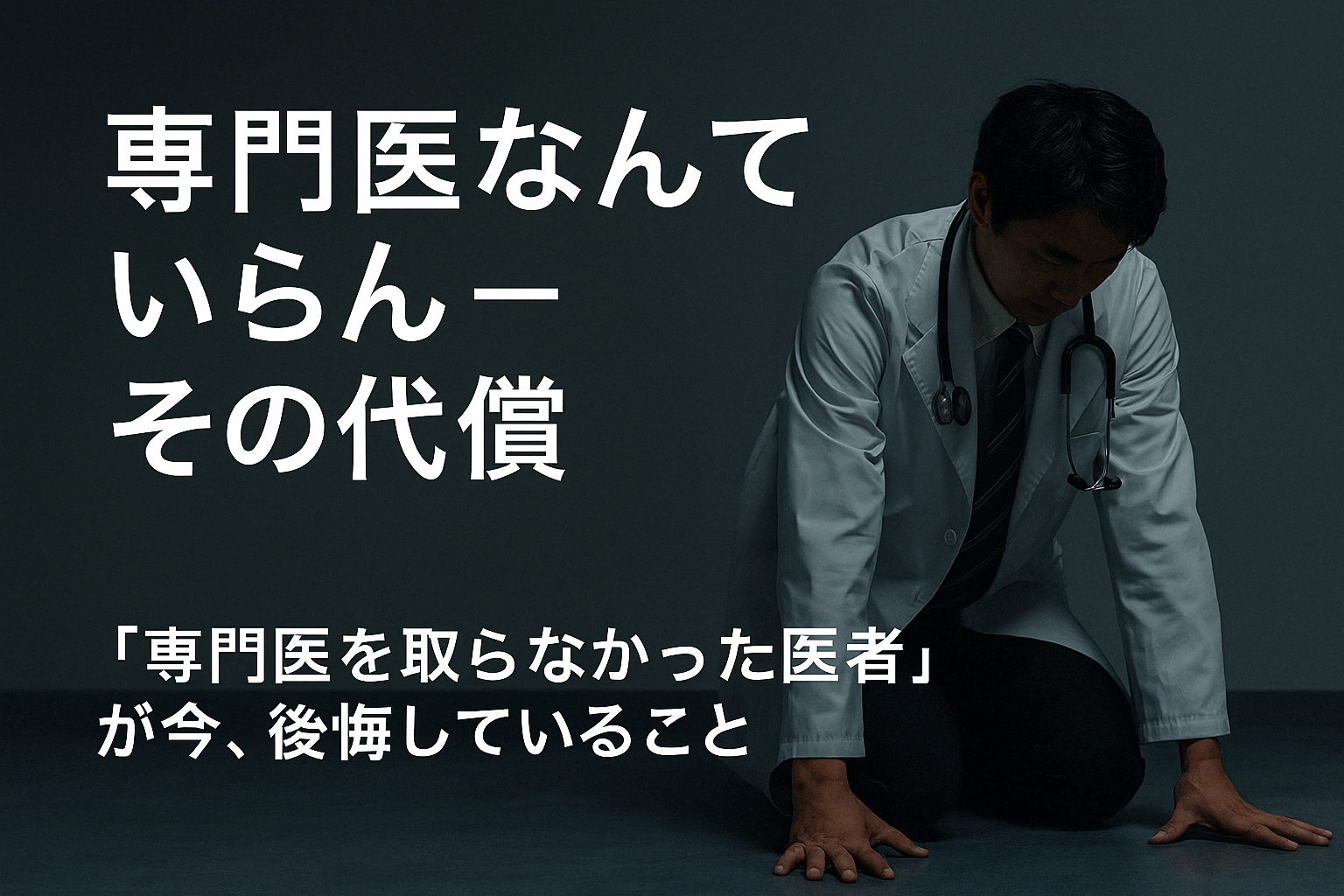

コメント